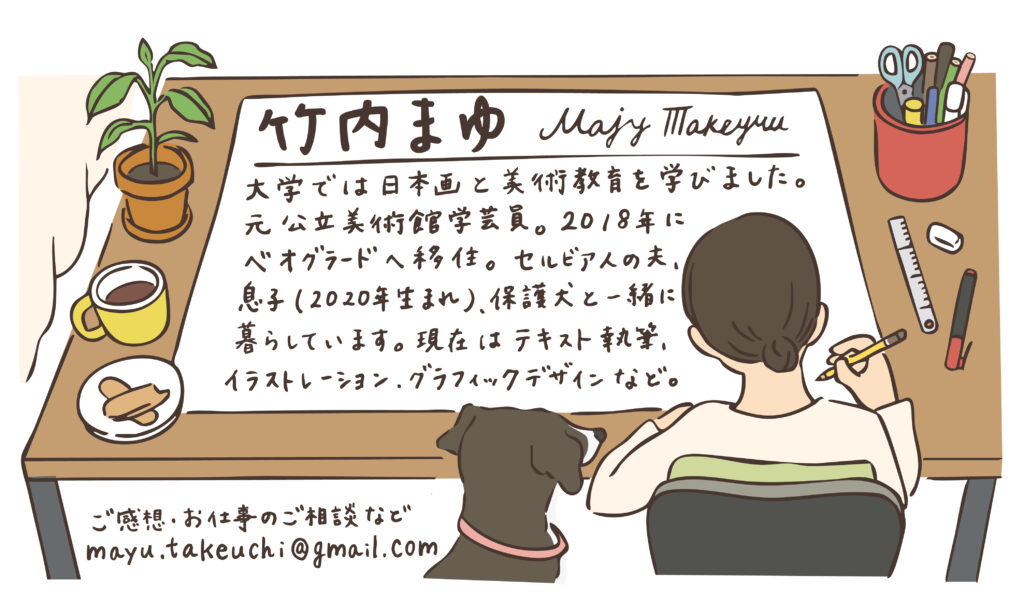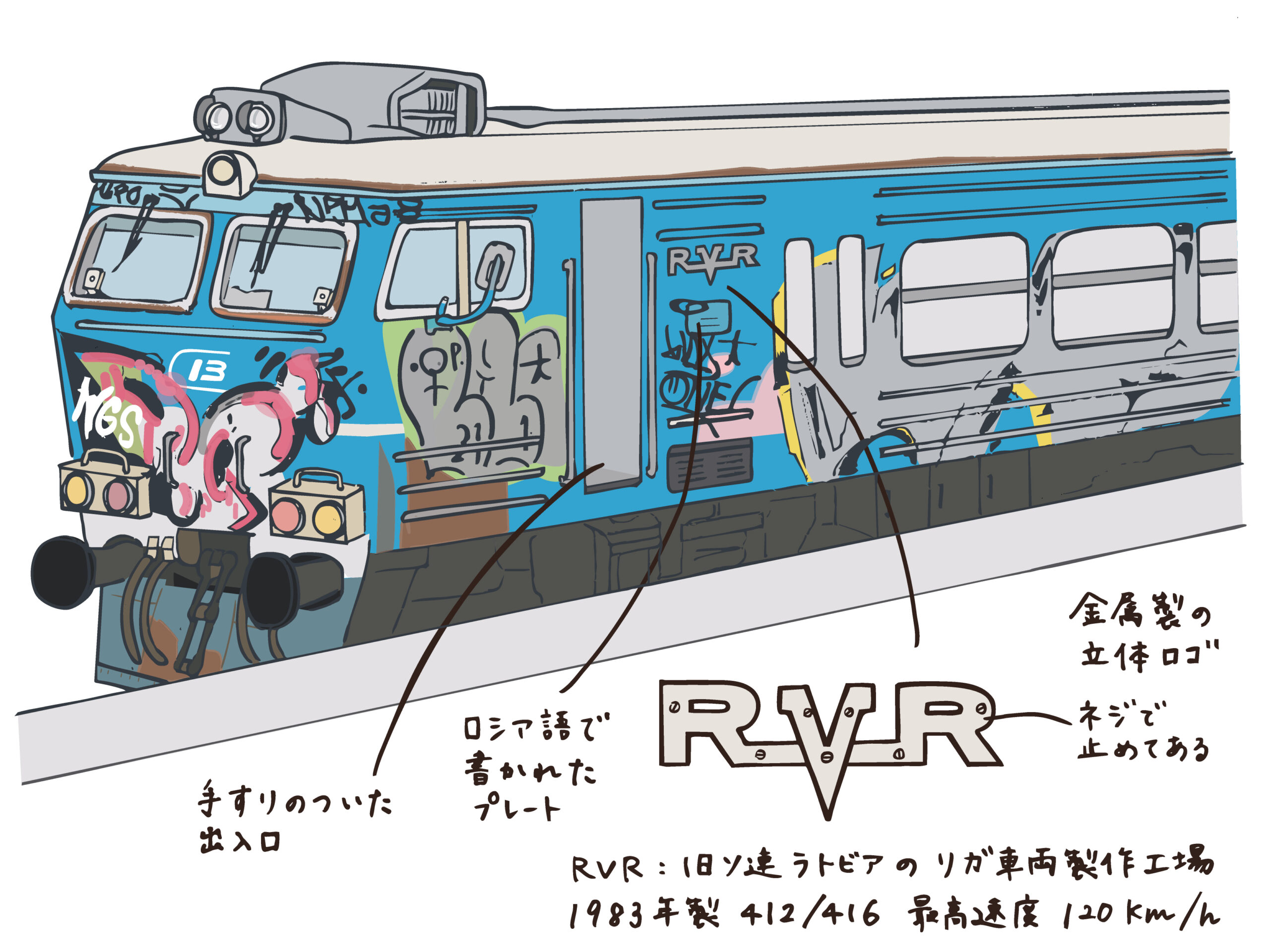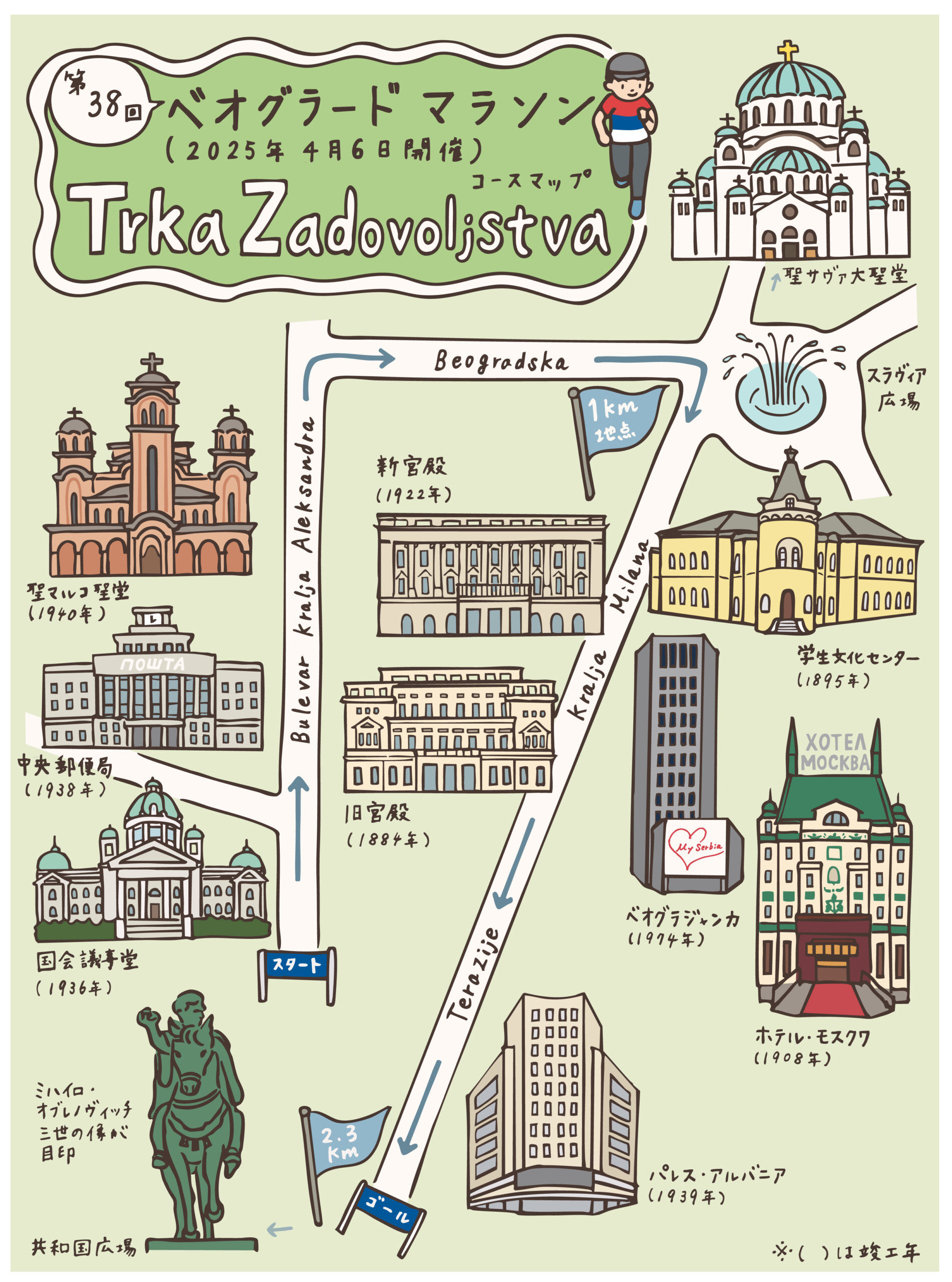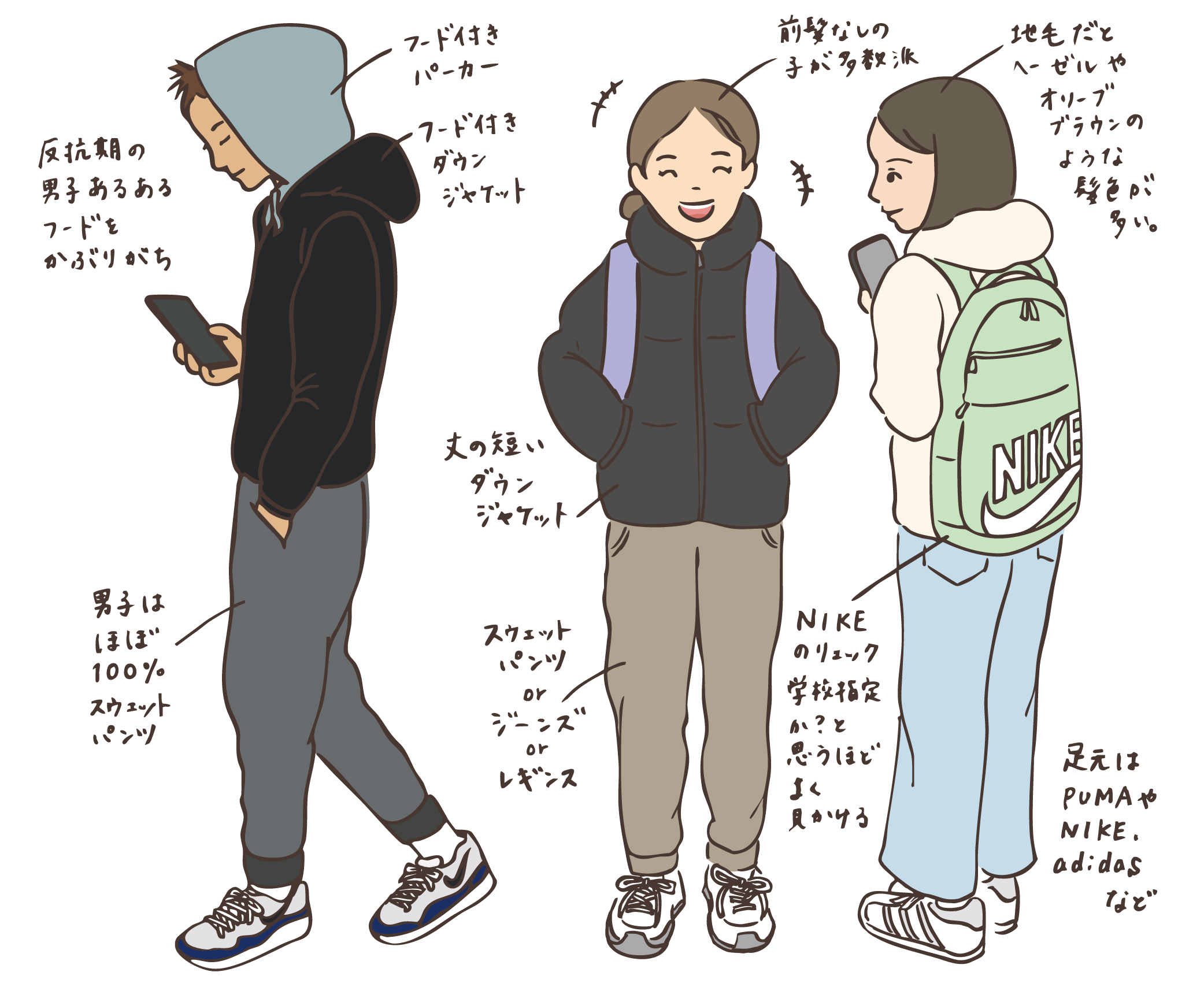【文と絵/竹内 まゆ】
長生きのワニMuja
ベオグラードには有名なワニがいる。カレメグダン要塞の中にある動物園の人気者で、オスのアメリカンアリゲーター、名前は「Muja(ムヤ)」という。なぜ有名かといえば、現在飼育下で世界最高齢のアリゲーターだからだ。2018年5月22日にギネス記録に認定された。
Mujaがドイツからベオグラードにやってきたのは1937年の夏。そこから88年経過しているので88歳以上であることは当然なのだが、この動物園での飼育が始まった時点ですでに成長した大きさだったという説もあり、アメリカンアリゲーターの通常の成長速度から考えると当時10歳から12歳と推定され、この情報が正しければ、現在はなんと100歳近い年齢ということになる。アメリカンアリゲーターの平均寿命は野生だと35から50年なので、その倍くらいの時間を生きていると言える。
Mujaが有名であるもう一つの理由は、3度の爆撃を生き延びたワニであることだ。第二次世界大戦下の1941年と1944年、砲撃と空爆によってベオグラード動物園は壊滅的な被害を受け、多くの動物たちが死んでいったがMujaは生き残った。3度目の爆撃は1999年のNATOによる空爆で、Mujaの住まいは被害を受けたものの命は助かったという。
実際に動物園に足を運び、Mujaの姿を見た感想は、”生きているのか死んでいるのか分からない”ということだ。微動だにしないワニ。しかしじっと見つめているうち、静けさの中に確かに生きている存在が感じられる。獲物をじっと狙っているような気がして恐ろしい。ワニの加齢は外見にどう表れるのだろう。哺乳類のように白髪が増えるわけでなく、年老いているのか否か、言われなければ分からないような気もするのだが、水中に沈むMujaの深黒の鱗板に年輪を見るような思いがする。

動物園のWebサイトによれば、Mujaの食事は週に1度で、5-6kgの肉を食べるということだ。実は野生のワニの場合、数ヶ月餌を食べなくても生きていけるという。餌の供給が不安定であったであろう戦時下において(飼育員たちの努力もあったにせよ)、このワニの独特な代謝は厳しい時代を生き抜くのに向いていたのかもしれない。
オスのアメリカンアリゲーターの標準的な体長は3〜4.5m、体重は450kgだ。鋭い歯を持ち獲物を捕食する姿は一見、凶暴に見える。しかし動物園で過ごすMujaの生活といえば、眠り、起きて、ごくたまに与えられる餌に噛みつき、消化し、泳いでの繰り返しだろう。単調だが平穏な生活だ。武力による衝突をくりかえす人間の狂気に比べれば、ワニの方がよっぽど穏やかな生き物に思えてくる。(ちなみに、日本語ではアリゲーターとクロコダイルは「ワニ」とひとくくりにされるが、アリゲーターは、攻撃的なクロコダイルよりも温和でおとなしい性格を持つ。)

Mujaには1960年代にメスのパートナーがいたという情報もある。しかし飼育員が誤って水槽にお湯を入れたことで死んでしまったらしい。人間の都合で元の棲み家から移動させられ、爆弾が投下される園内で生き延びたものの、パートナーを失った。人間に翻弄されてきたなんて苛酷な人生だろう。人の手が差し伸べられて助かったこともある。2012年に右前足の壊疽を起こし、すぐさま獣医による切断手術が行われた。この手術のおかげで現在のMujaは良い健康状態にあるという。
幸い、現在のベオグラードは政治的な混乱はあれど市民の日常は平和そのもので、Mujaが生きている間にこの街で戦争が起こりそうな気配は今のところ感じられない。しかしあらゆる地域で争いは終結に向かうどころか次々と亀裂が生まれている。私たちの日常と戦争が地続きであることを思うと、今私たちが生きている時代はもしや “戦後”ではなく”戦前”なのではないか…そんな考えが浮かぶ。
人びとがMujaについて語るとき、3度の爆撃を生き延びた”奇跡のワニ”、あるいは平和の象徴だと、特別な意味を与えるのは身勝手な考えだろう。Mujaを危険に晒したのは誰?戦争を起こしたのは誰だっけ?人間に都合の良いように解釈するのはMujaに失礼な気がしてしまう。どうかMujaには争いのない平和な世界で余生を過ごしてほしい。
燃えた図書館と50万冊の本
ある日、セルビア国立図書館を訪れた。館内での蔵書の閲覧は会員になる必要があるが、正面入り口のすぐ近くに展示室があり、蔵書に関連した企画展は誰でも無料で見ることができる。過去には雑誌『Zabavnik』の特集展示や挿絵画家の展示などがあり、小さい空間ながら工夫を凝らした展覧会がささやかな楽しみだったのだが、ここ最近は(少なくとも今年の3月以来ずっと)展示室は空っぽの状態が続いている。
この日は仕方なく、展示室の目の前にあるガラスケースを眺めることにした。燃えた本の断片が4つ、赤い布の上に並べられている。パネルの解説文を読む。1941年4月6日、Kosančićev venacにあった国立図書館はナチスドイツによる攻撃を受けた。失われた本の数はおよそ50万冊。12世紀から17世紀にかけてのキリル文字の写本や公的文書の約1500点、多くの地図や図版、雑誌や新聞、セルビアに関するオスマン帝国の文書、古い活版印刷の技術で作られた書籍、さらには政治史に関わる重要な資料や図書館の蔵書目録など。20世紀のヨーロッパにおいて膨大な本が失われた悲劇の一つであることを知った。

書物が炎で焼けてゆく情景を思い浮かべると、レイ・ブラッドベリの小説『華氏451度』を連想する。図書館と本が破壊されることは私たち人間にとって、思想と文化なき世界、ディストピアを象徴するものだ。国立図書館の焼失は、セルビア人の文化的アイデンティティの根幹を揺るがす出来事だったにちがいない。パネルの文章にあった”culturecide”という強い言葉に心が痛む。
廃墟となった図書館の中で、黒こげになった本を拾い上げた人、原形をとどめぬ文化の切れはしを、それでも図書館に収めようと思った人、再建された図書館の入り口に展示しようと思った人、かれらの気持ちを想像してみたい。戦争を通じて犠牲にしたもの、人びとが守りたかったもの、失わずにいられたものは何だろう…。もう開くことができない炭化した本の断片を目の前に、あれこれ思いを巡らせずにいられない。一次資料のみが伝えられる情報の力強さ。100人いたら99人が通り過ぎてしまうような地味な展示物なのだが、この図書館の入り口に展示されるのに、これ以上ぴったりな資料はないと思う。
ガラスケースから目線を上にあげると、壁面にはフランスの作家アンドレ・マルローの言葉が大きく印刷されている。
Je vois dans le destin de votre Bibliothèque le destin d’un peuple pour qui culture et liberté ne font qu’un.
(日本語訳:私はあなたの図書館の運命の中に、文化と自由が一体であると考える人々の運命を見ます。)
失われた書物は取り戻せなくとも、人びとの自由と文化を守ろうとする理想は破壊することができない。司書たちの強い意思を受け取ったような気持ちで、図書館を後にした。